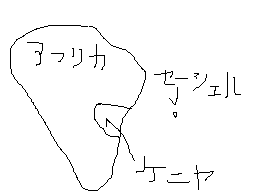
その昔、ケニヤに行った
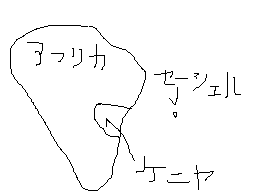
旅行中のメモはどっかにあるんでしょうが、それを見るとどうもそのまま書いてしまいそうなので、いい加減な記憶だけですべて書いてます。細かいところには勘違いなどもあるかもしれません。
↓以下、予定内容
なんでケニヤなのかっていうと特に理由はない。『少年ケニヤ』の世代でもないし。『ジャングル大帝』は好きだったが。ただ、そのころなんとなく第三世界にかぶれてた。まわりの友人たちがヨーロッパに長期で結構出かけてたんで、じゃあ僕は違うところに行こうってのも理由のひとつになったんだと思う。みんなと同じは嫌だということと、みんなに自慢できるからってことでしょう。僕は赤道越えます、とか。やな奴。生まれて初めての海外旅行がアフリカってのもかっこいいと思ってたんだろう。でも、これは行って本当に良かった。
<新社会科学研究会>
大学一年の終わりに、サークル活動そのものが嫌になって美術部を辞めたあとも、学内の政治学関連の研究サークルにはちょこっと顔を出していた。まあ、そのサークルはサークルと言えるようなものではなくて、実質的には自主ゼミが集合しているだけだったと思う。ただ、そういういいかげんなところがよくて、社会科学方法論ゼミなどを開いて、上級生らと『ドイツ・イデオロギー』やらソシュールやら読んでおったのですね。そのサークルの中に井出さんという人がいて、その人に誘われて私も学外の「新社会科学研究会」に入ったと。
その「新社研」では、社会科学全般、いろんな本を読んだり、いろんな人に話をしてもらったけれど、そんななかで、すこしずつアフリカとか政治学とか現代思想などに対して興味をもっていったのだろう。そんなことも含めて今から考えると、この研究会に参加したことの意味は大きかったのかなあ。いまでもつきあいの続いている人も多いし。研究会の後の飲み会でも本当にいろんなことを教わったなあ、としみじみする今日この頃です。
【追記:20251001】
<金>
<パスポート取得>
そこで、みんなどんなことをするかというと、まず本当の目的地を書かない。南米を一年間かけてまわるぞぉと意気込んでいる人間も「グアム行きまーす」とか嘘を書く。自己申告だし、チケットを持って来いと言うわけでもないので、こうした嘘を書いても向こうとしては確認しようがない。にもかかわらず、向こうはどこに行くのか知りたがる。同様に貯蓄残高証明も、誰かに金を借りて一時的に額を大きくしておいてから、その時点で証明書を出してもらって、それを窓口に持っていく。当然、借りたお金は翌日すぐに返すと。それでも向こうは納得するのよ。でも、残高証明は要求しつづける。馬鹿みたいでしょ。実際に僕がどうしたかはあえて書かぬが、とにかくこうしたうわべだけの官僚主義というか、阿呆なことを一生懸命している国家と、その委任事務を行っている地方自治体の担当者には本当にうんざりした。
ついでに言うと、当時はパスポートに使う写真にまでぐじゃぐじゃ文句をつけていた時代で、本当に嘘のような話だけれど、スーツにネクタイじゃないと駄目だとか窓口担当者はぬかしておったんですね。その頃はまだ住民票を松山においていたので、パスポートは愛媛県庁に申請したのだけれど、あれは愛媛県庁だけの話なのかなあ。日本中似たようなもんじゃなかったのかな。ちなみに、そのための写真を取ってくれた米田君も今は立派なプロのカメラマンになっております。嗚呼、人に歴史あり。
<予防接種>
<ビザ取得>
ところで全然関係ないけど、南麻布界隈で生活している人って、ふだん何を考えて生きているんだろうか。あのあたりって地下鉄の駅もないし、物価も高いだろうになあ。いや、この疑問にも深い意味はないけどね。もしかして、あのあたりの人は地下鉄も使わないし、高い物価も気にしないのかなあ。そんなこたあ、ないですよねえ。
<道祖神・ドゥドゥワールド>
<ブリティッシュ・エアウェイズ>
<ICI石井スポーツで買ったリュックサック>
ところがぎっちょん、いきなり石井スポーツのお兄さん、「あ、海外旅行ならフレームサックはやめたほうがいいですよ」と。あのてのフレームサックはフレーム自体が折れたら役に立たなくなるそうで、飛行場などで放り投げられたらアウトだと。登山用の深いリュックも荷物の出し入れの回数が多い海外旅行ではやめたほうがいいと。なるほどね。そんで、そういう旅行用には、かついだときに後ろの面にあたる部分が全部開くものが一番だと。それがなかなか良いのよ、細かいところまで良く出来ていて。防水加工の深い赤色。確か60リットル入りくらいの大きさ。でも、出発前にアパートでためしにこれを背負ってみたら、そのときに部屋にいた友人、関口君は「ガメラみたい」と言っとりましたな。
それでこの背負子のようなリュックですが、買って正解でした。ケニヤではすごく重宝しましたですね。幾多の乱暴な扱いにもよく耐えたなあと思う。一度など、マタトゥ(乗り合い自動車:後述)の屋根の上に放り投げられロープで縛りつけられたまま走っているうちに突然のスコールに襲われ、道路の左右もぐじゃぐじゃの泥沼になるような行程の果て、次の町に着いてみたら、リュックの外側はずぶぬれだったものの中に水はまったく入ってなかった、ということもありました。
ちなみにこの巨大なリュックサック。何か他に使うことがあるんだろうかと気にしていたんだけど、その後の私の人生のなかの妙なところで何回か役に立ってます。シカゴへ行くときとか。今も私のアパートの押入れの奥で眠ってますね。
【追記:20251001】
<厳重警備の成田空港の大嘘>
それで、成田でチケットを受け取って荷物を預け、出国手続き。当時の格安チケットって「空港でお渡しします」ってのが多かった。あれは不安感をいたずらに高める仕組みだったと思う。団体客として扱われるんだから文句は言えないんでしょうけど。
<セーシェル諸島>
ここまでの機内ではまわりの席に日本人多し。隣に渡辺公三さんという30歳くらいの男の人が座っていた。この人と話をしているうちに立教法学部の同じゼミにいた社会人学生の甥御さんだということがわかる。世の中せまい。当時、渡辺さんは国立音大の専任講師で文化人類学が専門でした。今は立命館に移っておられます。この時はフィールドにしている西アフリカへ行く途中だったそうです。渡辺さんとは旅行の最後にもナイロビ市内でばったり会って、二泊三日のサファリ旅行をご一緒することになります。
そんでもって、セーシェル諸島に着く。セーシェル諸島というのは、アフリカの東の海に浮かんでおります。小諸じゃなくて、コモロとかモーリシャスとか、マダガスカルとか、そんな島々の北にありますね。正確にはそのセーシェル諸島のなかのマエー島のビクトリアという町の空港に着きました。深夜の二時くらいに着いたんじゃないないかな。
ナイロビ行きのケニア航空の出発予定時刻が同日の午後11時くらいだったと思う。ほぼ一日あるわけです。ほとんどの乗換え客はホテルをとっていました。私はなんとかなるだろ、とホテルはとっていませんでした。そんなにばんばん飛行機が発着する空港でもないので、だんだん人気(ひとけ)はなくなっていきます。そしたら、機内で隣に座っていた渡辺さんもホテルを取ってなくて、結局、ずっといっしょにうだうだと空港のロビーで話しておりました。そのあとロビーのソファの上でちょっとは寝たのかな。やっと明るくなってきたので、街中に行ってみようかということになり、同じようにロビーで朝を待っていた日本人の父・母・娘という一家も誘って、ビクトリアの中心に向かいました。
ちなみに、この日本人一家の長女の方がケニアで日本人学校の先生をしてらっしゃるとのことで、このご一家はその彼女に会いに行く途中でした。その長女の妹がそのときそこにいたのですが、彼女の顔は年齢不詳でした。えらく整った顔立ちだったのですが、とにかく歳がわからん。ときどきそういう方っていらっしゃいますよね。大きなお世話でしょうけど。
そんでみんなで市場へ行ったり、昼飯を食ったり、海へ行って散歩したりと、楽しく時間をつぶしたわけですね。セイシェルはフランスの植民地だったのだけれど、渡辺さんがフランス語を上手に話すのでぜんぜん困らなかったし。マエー島の印象というのは、とにかくどこに行っても鳥ばっかしっていうことでした。島全体が猫屋敷ならぬ鳥屋敷みたいな感じ。本当に楽しゅうございました。
【追記:20251001】
<ケニヤ航空>
<ナイロビ>
着いた日からナイロビ市内をぶらぶらしてました。なにせ初めての海外旅行でございます。いきなり怒涛のようにケニヤ国内を巡り倒すってのも無謀かなあと思って、まず数日はナイロビ市内を歩くつもりだったんですね、最初から。朝ごはんを遠藤さんとこで食い、バスなどでダウンタウンへ。夕方までぶらぶらして、また遠藤さんの家に戻る。こんなことをしてたんですね。
初日はまず本屋で地図を買いました。日本ではケニヤの地図なんてなかったから。ナイロビの細かい地図も買った。その後、市場に行ったのかな。楽しかったなあ。ただ、当時はナイロビの治安が悪く、これは結構びびった。遠藤さんたちから行ってはいけないところは聞いていたので、そのあたりには行かず。でも、気候はとても気持ちよい。空気も乾いていて涼しい。アフリカのなかでもここが大きな都市になった理由がよくわかりました。日本人のあいだではナイロビの気候を「軽井沢のようだ」と形容することが多い。でも、ナイロビは軽井沢のようなすけこまし風の街ではない。軽井沢なんかと比べたらナイロビに失礼だろう。ほんとは、わし、軽井沢には行ったこともないが。行く気もないけど。
<スワヒリ語>
でも、これは私の語学能力が高いということではまったくなくて、いくつかの理由があるでしょうね。まず、第一にこっちが旅行者だということ。ケニヤで東洋人がでかいバックパックをかついでいれば、どう見てもよそ者だよね。ちょっとくらい変な言葉しゃべっても聞いてくれるよ。第二にはスワヒリ語の母音が日本語と同じ五つで、子音の発音もほとんど日本語と同じということもあるでしょう。文法などはともかく、発音に関しては日本語を使う人間にとってスワヒリは話しやすいです。第三には、行く前からスワヒリ語を全般的に憶えようなどとは思っていなかったということも関連していると思う。旅行中に必要ないくつかのフレーズに集中して憶えようとしたので、それらは何とか通じたし、相手の言ってることも何とかわかったということだと思う。
<ムゼー星野さんのこと>
星野芳樹ってどういう人かというと、簡単に言えば星野直樹の弟です。全然説明になってないか。この星野直樹ってのは、東大−大蔵省−満州国総務長官というコースをたどったおっさんで、東条英機におもいっきり好かれた人ですな。まあ、こういう人にありがちで、とことん毀誉褒貶ある人です。僕は嫌いだけど。
星野芳樹の他の兄弟も派手で、直樹のすぐ下の弟は星野茂樹です。トンネル工学の日本代表みたいな人。国鉄の長いトンネルはほとんどこの人の設計でしょう。関門トンネルとかね。だいたいこの兄弟の親もキリスト者として有名だったと思う。あんまり細かいことは憶えてないが。おばさんが津田塾の学長やってた星野あい、だそうです。『星野芳樹自伝』がリブロポ−トから出てるので、そのあたりに興味のある人は買ってください。
その自伝によると星野芳樹さん本人は1909年生まれだそうだから、僕が会ったときにはもう74歳くらいだったんだなあ。そうかあ、そうは見えなんだが。そんでこの星野さん、若い頃は左翼思想をもっていて、幾度か牢屋にぶち込まれたり、まあいろいろあるものの、上海で中国人のための学校を作っているうちに終戦を迎え、帰国。戦後初の参議院選挙で当選、労農党に属すも、一期で辞めて家族と共に群馬県沼田に引越して女子高の先生をやると。その後も本当にいろんなことをやってたみたいだけど、だんだんアジアにはまっていって、1954年に静岡新聞の論説委員となってからは、この新聞社の海外特派員として海外取材活動を依託されたそうです。それでアフリカに惚れてしまうと。
静岡新聞主幹となってからは静岡に転居したそうですが、そのころに静岡青年海外事情研究会をつくって、若者を海外に出すことの意義を知ったらしいです。1974年に静岡新聞社を定年退職したあと、なんと住居をケニアのナイロビに移してしまい、その年の11月にはケニア政府から「日本アフリカ文化交流協会」の認可を取ってんですね。そして、私財を投じて「ケニア・スワヒリ語学院」を設立すると。こうして見ると、その思想性はよくわからんが、行動力だけはすごいなあ。1988年にはケニアより故郷沼田に引き揚げて療養生活に入っていたものの、1992年5月31日、心筋梗塞のため沼田脳神経外科病院で永眠なさったそうです。
その星野さんが作った「ケニア・スワヒリ語学院」をナイロビでは「ホシノ・スクール」と呼んでたんですね。この学校、日本人留学生は全寮制で5か月間スワヒリ語を勉強するそうです。他にもアフリカの政治経済、文化、歴史などもいろいろ勉強できるそうです。
その星野さんとせっかく二回もナイロビ市内で会ったにもかかわらず、どうでもいいような話しかしなかったのはもったいないです。でも、もう遅い。少なくとも私が接した範囲では本当に親切でやさしい人でした。
<五十嵐さんのこと>
それで、その五十嵐さんは当時サバティカルをとってアメリカに留学中でした。大学で聞いていた噂では世界一周してから日本に一時帰国するということでした。でもケニアに来るなんて知らなかったんですね。ところが、ある朝、遠藤さんが「ナイロビのダウンタウンまで行くから車に乗せてってあげる」と言ってくれて、途中、彼の仕事の都合でとあるホテルに立ち寄ったですよ。そんで、そのホテルの前庭にとめた車の中で僕は遠藤さんを待っていたら、その前庭のテーブルで東洋人が一人、新聞を読んでおったです。五十嵐さんでした。いやあ、これはびっくりしたなあ。
その後、数日、五十嵐さんとナイロビをぶらぶらしたり、農村調査している研究者を訪ねたり、これは面白うございました。でも、何と言っても五十嵐さんとナイロビで会ってありがたかったのは、五十嵐さんが泊まっていた高級ホテルのシャワーを借りることができたということでございます。そのころ僕が泊まっていた道祖神の宿舎は「お湯は一人たらい一杯」と決まっていて、それで髪の毛も全部洗って、足りなければ水しかなかったんですね。アフリカなら水でもええやんけ、という方もいらっしゃるかもしれませんが、でもナイロビ、結構すずしいですからね。つらかったです。だから、五十嵐さんと一緒にいた数日は毎夕、ホテルのシャワーを借りてました。あれは本当に助かりましたです。
ちなみに、先日、五十嵐さんが新潟に来たとき「とんかつ屋」をはしごしました。ビールを飲みつつ、二軒のとんかつ屋に行ったのは生まれて初めてでございます。もう二度とないような気もするけど。ちなみに、行ったのは「青山:キッチン中」と「文京町:とんかつ太郎分店」。どちらも名店でございますな。食ったのは「ひれ肉一本揚げ」@キッチン中、「小カツ丼」「特製ロースかつ」@太郎分店。これらをおっさん3人でビール飲みながら食ったです。こう考えると新潟って、とんかつのレベルは高いぞ。ハイカロリー、ハイリターンな生活。
<農村調査>
まあ、いろいろあったけど、特に印象に残っているのはその土。やたら細かい赤土で、雨が降るとどろどろの泥流になり、乾くとほとんど煙のように舞う。自動巻の防水時計の内側にその土が入ってました。ちょっとびっくりでしょ。
あと、そこで働いている人たちが「コロンビアの気候が乱れてコーヒー豆の値が上がると嬉しい」と言っていたのも記憶に残る。コロンビアの人間も「ケニアの気候が……」と同じことを言っているんだろうけど。
<ホテル・イクバル>
ところがね、そんなある日、ダウンタウンの中を歩いていたら、とある交差点でいきなりアジア系の男に「日本人ですか」って日本語できかれた。「みんなイクバルにいますから、遊びに来ませんか」と彼は言うんですね。「みんなって誰のことじゃい?」とか思っていたんですが、少し立ち話をしているうちに、そのホテル・イクバルにたくさん日本人旅行者がいて、「みんな」で遊んでいるらしいということがわかってきました。
このとき受けた印象は忘れ難い。自分がわざと考えないようにしてきた世の中のある部分を見てしまった感じがした。大げさかなあ。アフリカくんだりまで来て、どうして日本人旅行者が群れなければならないのか。個人旅行でしょ。わざわざ一人で成田を出て、それがまたナイロビで集う。すごく不思議な気がした。
彼らがマリファナやってるとか、ドラッグきめてるとか、そういうことは想像で語ってはいけない。ただビール飲んで騒いでいるだけかもしれないし。馬車馬(ばしゃうま)のように東京で1年働いて、稼いだ金でアフリカに来て2年暮らす。そういう生活も、現代の閉じられた管理社会に対する異議申立てとしては認めよう。会社員になってネクタイしめるだけが人生じゃない。今でも基本的にはそう思う。
でも、イクバルでうだうだと遊んでいる(ように見えた)彼らが私には本当に不思議でした。私だっておちゃらけた旅行者だし、五十嵐さんのホテルのシャワーは借りてるし、道祖神の宿に泊まってるし、偉そうなことは言えない。それでもやっぱり不思議だったのは「彼らはあんなに集まっていったい何が楽しいんだろう」ということだ。このときの「みんな」に対する違和感(と言っていいと思う)は、人間の集団化ってなんだろうという疑問につながっていたと思うし、国民とか国家とか民族とか、だんだん大げさになるけれど、そうした集団原理に対して考えさせる何かの契機だったのかなあ、と今となっては思うのですね。そのころ漠然と考えていたことに対する突発的な見本だったとも言えますね。
ちなみに、東京などで1年働いて、その金を使って第三世界で遊んで暮らすということを繰り返している日本人には、その後の海外旅行でも何回か会いました。中には面白い人もいたのは確かです。でも最低な奴もいて、なかでもひどかったのは、東南アジアで幼女買春に走っている塾講師でした。東京の塾で子供にものを教えて、そこで稼いだ金でバンコクの子供を買う。なんなんだろうなあ、これは。
日本政府発行のパスポートをもって旅行している人間にとって、こんな奴までも自分とおなじ「みんな」として考えなければならないというのはきついです。ここでその腐れ塾講師の実名出したろうかとも思いますが、いろいろ面倒なことになっては困るのでやめておきます。本当はそいつの名前も覚えてないし、アドレスの交換なんかもしてないですけど。ちょっと脅しね。何の脅しかわからんが。
ナイロビの街中をうろうろしていたときでした。こんどは黒人のおにいさんが声をかけてきました。人の良さそうな奴、というよりも、妙におどおどしてて情けない感じ。大丈夫か、こいつ、と思いました。そのおにいさんは、ちょっと話をしたいから喫茶店へ行かないかと言う。当然だけれど、こっちは圧倒的に暇なもんだから、つきあいました。すぐ近くの喫茶店みたいなところに行きました。
そんで、こっちはアイスクリーム、むこうはコーヒーとミートパイを頼みました。話を聞いていると、彼はウガンダから逃げてきたということでした。首都のカンパラに住んでいたんだけれど、自分は反政府派なんで生きてはいけないと。その頃のウガンダはアミンを追放してはいたけれど、オボテはまだ事態を収拾できず混乱が一層深まっていた頃かな。まだムセベニは大統領になってないですね、たぶん。ま、いろんな意味でカンパラが混乱していたのは事実です。
おにいさんはずっと自分の境遇を嘆いています。つらい、悲しい、人生真っ暗。そうかもしれんけど、それを極東の島国からきたぼんくら大学生に延々と話されてもなあ。でも、私もずっと聞いてました。へーとか、はーとか、大変だねえとか言いながら。それで「もうそろそろ俺は行くよ」と言ったら、彼(うが)は金がないと言ったんですね。以後の会話……
越智:なんじゃそりゃ。
金がないと向こうが言ったとき、すぐにだまされたことに気づきました。彼が本当にウガンダから来たのか、それとも失業中のケニア人か、そんなこともどうでもよろしい。とにかく何かの食いものにありつくために、近寄ってきたこと、それがとにかく腹立たしく、今でも覚えているほどでかい声で「カンパラに帰れ!」とびっくりマークつきで怒鳴ったんですね。
結局、僕が彼の分まで払ってお店を出て、彼とはそのまま話もせず別れました。今、どこで何をやっているのか知りませんが、もしこのページを見ていたら、あのときのコーヒー、ミートパイ代は返してもらいたい。
後でケニア在住の日本人から聞いたところによると、ウガンダから逃げてきたと言いつつ人にたかるというのはよくあるパターンらしいですね。他の被害者のなかには、すごく同情して過剰におごってしまう人もいたらしいです。公園などで話を聞いてもらっているうちにいきなり強盗化する奴もいたそうで。「越智さん、コーヒーとミートパイで済んでよかったじゃないですか」と言われたけど、でもやっぱり思い返すだけで腹が立つ。
それはともかく、ナイロビからナクルという町へまず向かう。その移動はマタトゥという乗合自動車。車種はバンみたいなのから、小型バス、トラックの荷台を椅子席に改造したようなやつまでいろいろ。日本の中古車などを使ったりしているのもあって「草津温泉相模屋旅館」とか書いてあるマイクロバスがケニアの大地を走っとります。
そのマタトゥ、乗り合い自動車なんで満員になるまで出発しません。だからマタトゥの駅(といってもただの広場ですが)に行くと「君はどこに行くのか。私のマタトゥに乗りなさい」とお兄さんたちがたくさん寄ってくる。そんななか、早く満員になりそうなのを見つけて乗るわけですね。
もちろん一人でも多く乗せたいので、とにかくつめこめるだけつめこむ。さすがにこれで出発だろうと思っても、まだまだ詰め込む。で、みんなの荷物もあるから中は本当にきつい。自分の椅子の下に羊が寝てたこともあるし、ニワトリが籠から逃げて車内を跳びまわったこともあった。
このマタトゥがまたすごいスピードで走る。当時は(って今もそうなのかもしれませんが)道も悪かった。けっこう大きな穴ぼこが道路のアスファルトに空いていたりする。牛も歩いていたりする。だから事故も多し。道端にころがっているマタトゥも見たなあ。なかに乗っかっていた人はどうなったんだろうかと思うと怖かった。でも他人の事故を怖がっている場合じゃなくて、自分のマタトゥもとんでもないスピードで走る。結果的には一回の事故もありませんでした。が、あれは本当に怖かった。
このとき以降、基本的にはどこの町に泊まるときにもマタトゥのなかですすめてくれた宿に泊まりました。それで大きな問題もなかったす。なかには「うちに泊まれ」といってくれる人もいましたが、それらは丁重にお断りしておりました。
そのナクル、町の近くにナクル湖というでかい湖があります。ピンク・フラミンゴで有名。ジョン・ウォーターズの映画とは無関係。本当にピンクのフラミンゴがたくさん湖にいるらしい。
それでせっかくここまで来たのだからと、宿に荷物を預けて湖に向けて徒歩で出発。街中で場所を聞き、歩いていけるかも確認しました。ところが、遠い。遥かなり、ナクル湖。
よく日本の地方差別みたいなギャグであるじゃないですか。どこかの田舎でおばあさんに道を聞いたらえらく遠いのに「ほんのすぐそこ」みたいに言われてひどい目にあったとか。それを極端にしたようなもんだったんでしょうか。とにかく行けども行けども着かない。不安にもなってくるし、途中で何軒か民家もあったので聞いたら、道は間違ってない、もうすぐだよと皆さん、おっしゃる。それでも遠い。2時間くらい歩いたんじゃないかなあ。ケニアの人たちの徒歩での行動半径はとんでもないものでございました。極東の島国の軟弱な馬鹿は疲れ果てましたです。
ケニアの国立公園は車がなければ入れてもらえません(たぶん今もそうだと思う)。ナクル湖も国立公園です。公園の入口で待ってればサファリ・ツアーの車が適当に来るからそれにヒッチハイクして乗せてもらえば良いよ、とナクルの宿のおばさんの意見です。待ちました。でも、何も来ません。やっと1台来てみたら、満員。満員どころか5人乗りの車に7人くらい詰め込んでたんじゃないか。乗せてくれと言えるわけがない。
ということで、公園の入口ゲートあたりをうろうろと歩き、遠くからナクル湖を見ました。遠い湖の上にべったりとピンク色の帯が見えたので、あれが大量のフラミンゴだったんでしょう。サファリ・ツアーは旅行の最後にお金が余っていたら行こうと思っていたんで、このときはナクル湖国立公園に入れなくても、それほど残念とは思いませんでした。
ナクルにまた2時間歩いて戻ります。今度は前もってわかっているからあんまり疲れなかった。行き先不明ってのがいちばん怖いんですね。そんで宿でカレー食ってビール飲んで寝ました。宿といっても街中の小汚い食堂の2階の小部屋。トイレ、シャワーは共同。でも日本を離れ、ナイロビも離れた初めての晩。自分のことを知っている人間はおそらく半径5000キロくらいは一人もいない。すごく解放感があってうれしかった。人生、ところどころでとんでもない解放感に突然襲われたりしますが、あの晩もそうでした。
<つづく>
「理由」のところに書き忘れたけれど、そのころ「新社会科学研究会」という会に入れてもらってた。名前がすごいでしょ。貿易論とアフリカを専門にしている古沢紘造さんという駒沢大学の先生と、立教で政治過程論を教えていた五十嵐曉郎さんたちが中心になってやっていた研究会兼読書会。ちなみにこの古沢さんのアフリカ研究仲間の一人が、今の大学の僕の同僚兼飲んだくれ仲間の原口武彦翁であるというあたり、世の中不思議なものです。
この文章を最初に書いたときに同僚だった原口武彦先生は2005年3月に新潟国際情報大学を定年でご退職され、その後もアフリカ研究を続けられていましたが、2025年5月9日に他界されました。ご冥福をお祈りします。
そんでもってどっか行こうと思って最初に考えるのが金ですね。仕送りはもらってたのだけれど、さすがにアフリカ行くからお金ちょうだいとは言えない。そこで、それまではあんまりやってなかったアルバイトをいろいろやり始めた。客商売は嫌いだったので、東京では六本木にあった塾の先生、松山の実家に帰ったら測量設計会社の下働きを中心に、小金を貯め始めました。ただ、多分これは旅行の前だけじゃないんだろうけれど、そこそこの金が貯まると「この旅行にはこれほどの金を使う価値はあるんだろうか」などと、突然ネガティブな気持ちになったりした。旅行前ブルー。皆さん、経験ないですか。そういうこともありながら、なんとか50万円くらい貯めた。
今では信じられないことだけど、1983年頃はパスポートの申請は本当に面倒だった。まず、ここでも金。金のない奴にパスポートは出さない、などと国家は馬鹿なことを言っていたわけですね。パスポート申請に貯蓄残高証明を要求していた。それで、その残高もハワイやグアムなら小額(と言ってもそこそこの額)を要求し、ケニヤなんて言ってしまおうものなら、平気で百万円くらいは要求していた時代です。まず、その計算の根拠になる往復航空券を正規料金で計算。さすがにこの時代でも正規料金で飛行機に乗る阿呆なんていなかったのに、信じられないですよね。
結局、予防注射を何本打ったのかな。コレラ、狂犬病、破傷風は覚えております。黄熱病も打ったか。注射打つために品川の検疫所にも行ったし、有楽町の交通会館にも行ったなあ。サンシャイン60の中の病院にも行った。あれはコレラだったかな。一番痛かったのもコレラだったような気がする。こんなたくさんの注射を一度に打つと死んでしまうので、あいだをあけて打たないといけない。そのうえ、それぞれの有効期間も考えないといけない。そんなことを考慮しつつ、何ヶ月かかけて、文字通り免疫力を付けていきました。
ケニヤ大使館は南麻布あたりにあったと思う。やっととったパスポートにビザを書き入れて貰うためにケニヤ大使館まで行った。エチオピアにも行くかもしれなかったので、再入国可のビザを申請したら、そこについてちょこっと質問された。これが人生初の英語での他国籍の人間との問答(というほどのものではないか)でした。嫌な感じもなく、すんなりとビザをくれました。
ケニヤまでの航空券をどこで買うかですが、ケニヤへの航空券と言えば、当時はアフリカ専門のこの旅行会社くらいしか扱っていなかったんじゃないでしょうか。「新社会科学研究会」の古沢さんにもここがいいよって紹介されていたし。目黒駅前のビルの一階にあった。ここはナイロビにも支店というか、現地法人というか、そういうものを持っていて、ケニヤ関係では一番だということでした。今も多分あるんだと思う。それにしても「道祖神」っていう名前が……。
それで、道祖神では当初、成田―カラチ―ナイロビというパキスタン航空のチケットを19万円で用意してくれた。とにかく着ければいいのよ、ということで航空会社にはぜんぜんこだわってはいなかったし。ところがぎっちょん。当初の予定では8月のあたまに成田を出、一ヶ月くらいケニヤで遊び、8月末に帰るということだったのだけれど、7月の中旬くらいか、とにかく結構間際になってから、「ナイロビへはパキスタン航空は飛ばなくなりました」っていう連絡が道祖神から入ったのでありました。なんでも空港使用料をめぐってケニヤ政府とパキスタン航空のあいだの関係が悪くなったとかで、当分のあいだはカラチ―ナイロビは飛びません、と。そんなこと突然言われてもなあ、と困っていたら、ブリティッシュ・エアウェイズのチケットをディスカウントしますと道祖神が言う。今はどうか知らないけれど、当時BAと言えば高級な航空会社の代表みたいなイメージがあって、とてもじゃないけど学生が乗ったりはしないとこでした。そのBAで行くことして、成田―台北―コロンボ―セーシェルと飛び、セーシェルからナイロビまではケニヤ航空。それがたしか30万円だった。ほぼスケジュールは同じ。ちょっと高いような気もするが、まあしょうがないです。何といってもBAだし、とか無理に納得したような記憶があります。
どんなカバンで旅行に行くかってのは、結構その旅行自体の性格を決めるもんですね。一人旅だし、学生だし、なんつってもアフリカだぜ、というのでフレームサックを買いに行きました。あのアルミのフレームがついてるでかいやつね。憧れてたんですよ、あれを使う旅行に。行ったのは新大久保にある「ICI石井スポーツ」。懐かしいなあ。あの日、生まれてはじめて新大久保駅で降りたんじゃなかったか。
結婚後はこのリュックを使用するような旅行はしなくなりましたし、さすがに置きっぱなしにするわけにもいかず、ゼミ生の一人がアジア大陸を陸路で香港からパレスチナまで横断するということになったとき、彼にあげました。役に立ったそうです。そりゃそうだろうなあ。
それで生まれて初めて成田へ。とか言っても当然、この旅行は準備も含めて「生まれて初めて」のことが多いのだけれどもなあ。その頃、サミットがあったのか、誰か政治家が来日していたのか忘れたが、大人数の機動隊やら警察やらで、もう成田も開港してからだいぶたってたと思うし、落ち着いてもいた頃のはずなんだけど、ものものしいところでした。今とは違ってターミナルもひとつだし、そのターミナルまでも京成や国鉄の駅からバスで行ったんじゃなかったっけ。京成だけかな、バスが必要だったのは。そんで、その途中、いろんなところで検問のようなものがあったのだけれど、これが全部、笊(「ざる」って読んでね)。ほとんど点検するふりをするだけで、かばんの中も、チケットの名前もほとんど見ない。ええのか、こんなんで、と思ったのをおぼえております。
BAの747は台北、コロンボと中継しつつセーシェルへ。最初の予定ではコロンボの空港から街中へ出て行けるはずだったのだけれど、ちょっとややこい民族紛争が起こっていて危ないからということで空港内で時間待ち。大学でエスニシティなどということを勉強し始めていた頃だったので、妙にしみじみしてしまった。
機中で偶然隣席となり、セーシェルでお世話になり、サファリ旅行も一緒に行った渡辺公三先生は、こちらが大学院進学を決める際など、その後も折あるごとに会っていただいて相談に乗っていただいたり、ご著書をご恵投いただいたりしていましたが、2017年の暮れに他界されました。ご冥福をお祈りします。
セーシェルを夜中に出て、一路ナイロビへ。ここからケニア航空に乗り換え。どれくらいの時間がかかったかは忘れたが、食事も一回は確実にでた。五時間くらいかな。よくわからん。でも、その食事がカレーだったこと、スチュワーデスのおねえさんが1940年代半ばの『トムとジェリー』に出てくるメイドのおばさん的な動き方だったことなんかを憶えています。ケニア航空にも悪い印象はなし。カレーも美味しかった。
それで早朝にナイロビに着きましたですよ。空港に道祖神の現地スタッフの遠藤さんという人が迎えに来てくれてました。到着直後のナイロビでは道祖神の経営している宿に泊まることにしていたのでした。宿といっても、遠藤さんの家に間借りするみたいな感じ。遠藤さん、元気なんだろうか。面白い人でした。
今はどうか知らんけど、そのころ日本語で書かれたスワヒリ語の教科書はなかった。旅行者用の簡単なガイド本が一冊あって、それと英−スワヒリ語辞典を買ったような記憶があるなあ。それらを使ってちょこちょこと独学で勉強してからケニヤに行きました。でも、行ってみれば意外に通じたのよ、これが。
そのころのナイロビには「ホシノ・スクール」というのがあった。みんなから「ムゼー星野」と呼ばれているおじいさんがつくったスワヒリ語学校。ナイロビにそんなに日本人がいるわけもなく、道祖神の人たちもよく知っているおじいさん。僕もナイロビにいる時に、二回ほど会った。一度は星野学校で。もう一回は街中で。気さくな人で、親切にしてくれました。ところがぎっちょん、このおじいさん、帰国後に知ったのですが、あの<星野芳樹>だったんですね。わしは知らんかった。ケニヤにいる時にそれを知ってればなあ。いろんなことを聞いたのに。
立教大学法学部には基礎文献講読という1年ゼミがありました。今はすこしカリキュラムが変わっているそうですが、当時は週二回もあるにもかかわらず、もらえる単位は少なく、内容は難しくてきついという基礎ゼミでした。そのゼミは専任教員と助手が組んでおこなうのですが、その専任教員が上記「新社会科学研究会」で書いた五十嵐暁郎先生だったんですね。
そんで五十嵐さんと行った農村調査ですが、これはなかなかすごいところでした。ナイロビから車で1時間くらいの山村。あたり一面の山肌がコーヒー畑。
五十嵐さんがナイロビを離れてからは、また一人でダウンタウンを歩き回る日々となりました。大きな市場とかナイロビ大学とか行きました。両方ともとても面白いところでした。治安は悪い都市だけれど、やっぱり面白いところは面白いのよ。特にああいうアフリカのでかい市場なんかは生まれて初めて見るわけでしょ。いくらいても飽きなかった。食いものもおいしかったし。
<ウガンダからのおにいさん>
いろんな人がナイロビにはいるというのは知っているつもりだった。良い人もいれば、悪い人もいる。あたりまえだ。でも、その悪い人が目の前にいて、私をだましていたということがわかったとき、私、激怒しましたです。それまでの人生において「だまされる」ということに免疫がなかったんでしょうね。ちなみにその被害額、コーヒー1杯とミートパイ1個分でした。
<マタトゥ>
うが:とにかく金がない。
越智:ほんじゃ、これは誰が払うんじゃい。
うが:でも僕は金がない。
越智:知るか。おまえが注文したんだから、おまえが払え。
うが:でも金がない。
越智:ここで働いて払え。
うが:ウガンダ人だから雇ってくれない。
越智:じゃあ警察に来てもらおう。
うが:ウガンダ人だからひどい目にあう。
越智:だからと言ってこっちが払う義務はないぞ。
うが:でも金はない。
越智:最初から金がないくせに人を誘ったのか。だますつもりだったんじゃな。
うが:だますつもりはなかった。話をしたかっただけだ。
越智:それを「だます」って言うんじゃ、ぼけ。
うが:いや、違う。
越智:ぐじゃぐじゃ言うな。どあほ。カンパラに帰れ!
うが:しーっ、そんな大声ださないでよ。ウガンダ人だということがばれるから。
などという日々をナイロビで送っていたのですが、じゃあ、もうそろそろナイロビの外へ出るかという気になって、向かったのがトゥルカナ湖。別に理由もない。ケニアの北西の端っこ。ここまで行ってみたらどんなもんだろうと。海のほうは開けてそうだったし、それはまた後から行こうと思っていたんですね。体力のあるうちに面倒そうなほうへ行っておこう、と。でも結局、どこに行っても楽しくて、体力がなくなることもありませんでした。そんな感じで食べつづけているうちにケニアで体重増やして日本に帰ることになりました。
<ナクル湖>
それでナクルです。一気にトゥルカナまで行くのもつまらないし、途中、いろんなところに寄ってみたかったと。ナイロビからマタトゥで3時間くらいだったんじゃないかなあ。で、着いたら宿をなんとかしないと……とか考えている暇もなく、マタトゥのなかでまわりの人間がいろいろと聞いてくる。中は何せ狭いですからね。黙ってるよりもおしゃべりしてたほうがみんな気が楽だし。どっから来たんじゃい、とか。どこに泊まるんじゃい、とか。そんなことを聞いてきます。そんなおしゃべりをしているうちにナクルではあの宿が良いぞとか教えてくれるんですね。
越智の表ホームページへ
越智の裏ホームページへ
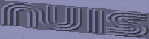 ←新潟国際情報大学のホームページへ
←新潟国際情報大学のホームページへ